
ヤモリサミット回顧録|壁紙修繕におけるDIYとプロの境界線
ヤモリサミットの司会席に腰を下ろしたとき、会場の空気にふわりと期待感が立ちのぼるのを感じた。
かつて壁紙の修繕は、職人だけの世界にあったもの。
けれど今では、DIYという文化がそっと日常に入り込み、少しずつ暮らしの中に根を張り始めている。
プロの知恵と、参加者たちのまっすぐな好奇心が出会うこのひととき。
いったいどんな発見が生まれ、どんな可能性が顔をのぞかせるのだろう――
そんなことを思いながら、私はそっとマイクに手を伸ばした。

DIYとプロ、その境界線を探る
このテーマは、会場にいらした皆様にとっても、きっと大きな関心ごとだったはずだ。 住まいを自分の手で整えてみたい、という想いはあっても、 私は司会として登壇者の言葉をつなぎながら、 |
登壇した 小池光孝 氏は、職人歴30年以上という、まさにベテランのひとり。 参加者の多くは、「新しい材料を使ったほうが、きれいに仕上がるんじゃないか」と考えていたようで、 けれど小池氏は、穏やかに続ける。 |
さらに印象的だったのは、小池氏が語った“初心者が陥りやすい勘違い”についての話だ。 多くの人が「まずは小さな空間から始めたほうが簡単だろう」と思い、 「むしろ、家具のない広い壁面のほうが貼りやすいし、成功率も高いんです」 その瞬間、会場のあちこちから小さな驚きの声がもれた。 |
一方で、水まわりの修繕については、少し厳しい現実も語られた。 トイレや洗面台を取り外すとなると、どうしても配管まわりの作業が避けられず、 「そこは、迷わずプロに任せてほしい」 同席していた木本氏も、重ねるように続ける。 その瞬間、会場の空気がすっと引き締まったのがわかった。 |
このやり取りを通じて浮かび上がってきたのは―― どんな材料を選ぶか。どこまでを自分の手でやるか。 そんなふうに役割を分け合うことで、 登壇者たちのやり取りを聞きながら、私はふと、 |

Point of View
小池氏の言葉には、現場で積み重ねてきた経験の機微が静かににじんでいた。 初心者がつまずきやすいところを丁寧に示しつつ、挑戦する楽しさにもそっと光を当ててくれる。 その気遣いとこだわりに、司会として心から敬意を抱いた。 プロの視点を惜しみなく共有してくださる姿勢こそが、これからの内装業を支えていくのだと、あらためて感じている。

砂壁とペイント、新しい挑戦のかたち
| 古い日本家屋や賃貸物件に残る「砂壁」は、多くの参加者にとって避けて通れないテーマだった。 その話題が登壇者の口から出た瞬間、会場の空気がふっと変わる。 観客の表情が一斉に引き締まり、うなずきながら聞き入る姿が、あちこちで見受けられた。 実のところ、私自身もこの話題には特別な思いがある。 砂壁は、見た目には素朴でどこか温かみもある。 けれど、ひとたび劣化が進んでしまうと、ほんの少し触れただけで、ぽろぽろと崩れてしまう。 私たちプロにとっても、何度となく頭を悩ませてきた、手強い相手なのだ。 だからこそ、「DIYでどこまで対応できるのか?」という問いには、 誰もが強い関心を寄せていたのだと思う。 |
| 小池氏は、経験豊かな視点からこう語った。 「砂壁は、シーラーやパテで固めようとしても、思った以上に時間も手間もかかるんです。 だから私は、ベニヤで封じ込めてしまう方法が、いちばん現実的だと考えています」 その言葉に、少し驚いた様子で目を丸くする参加者もいた。 多くの人が、「塗って補強するほうが正しい」と思い込んでいたからだろう。 けれど、小池氏の説明が進むにつれ、会場には徐々に納得の空気が広がっていった。 というのも、砂壁の下地にはモルタルやプラスターボード、土壁など、さまざまな種類があり、 それぞれに合わせた対処が必要になるからだ。 倉田氏も「まずは、どんな下地かを見極めることが何より大事です」と語り、 DIYにおいては「作業」だけでなく、「判断」こそが要になるという視点が強く印象づけられた。 |
| 話題はやがて、ペイントへと移っていった。 小池氏は、「壁紙の上から塗れるペイントは手軽なんですが、 ホームセンターで手に入る塗料だと、どうしてもムラになりやすい」と語る。 確かに、プロが使うような塗料を選べば、美しい仕上がりも期待できる。 けれど、そこには材料の扱い方や下地処理など、知識と経験が欠かせない。 参加者の多くは、「DIYだからこそ、簡単にできる方法」を求めていた一方で、 「せっかくなら、ちゃんと美しく仕上げたい」という思いも捨てがたかった。 その両方を叶えたいという願いが、このテーマをより深く、複雑なものにしていった。 |
| 私は司会者として、このやり取りを見守りながら、静かに思っていた。 内装の世界には、確かに新しい風が吹き始めている。 DIYは、単なる“節約の手段”ではなく、 “暮らしを楽しむ文化”として、少しずつ受け入れられはじめているのだ。 壁紙を自分の手で貼ってみる。 ペイントで部屋の雰囲気を変えてみる。 そんな小さな挑戦が、住まいへの愛着を育み、日々の暮らしを少しずつ豊かにしてくれる。 けれどその一方で、砂壁のように手ごわい素材もある。 DIYだけでは難しい領域が、たしかに存在している。 だからこそ、「ここはプロに頼もう」と判断する勇気もまた、 安全で心地よい住まいづくりには欠かせない要素なのだと、あらためて感じていた。 |
| このセッションを通じて、参加者の多くが気づいたのではないだろうか。 「どこまで挑戦し、どこからプロに託すか」――そんな視点が、これからの住まいづくりには欠かせないということに。 DIYでできることを楽しみつつ、難しい部分は無理をせず、プロの手にゆだねる。 その柔軟な考え方こそが、これからの内装業に新しい光をもたらしてくれる。 私はそう信じて、セッションの余韻を噛みしめていた。 |

Point of View
砂壁やペイントといった難しいテーマに対しても、小池氏は実直で誠実な視点を示してくださいました。 下地の種類をひとつひとつ丁寧に説明しながら、DIYの可能性と限界を、分かりやすく伝えてくださったことに感謝しています。 材料選びのひとつにまでこだわりが宿っていて、その姿勢こそが参加者にとっての大きな学びであり、 これからの内装業を支えていく、ひとつの指針になると感じました。

道具と知識が未来をひらく
| プロの世界を支えてきたのは、確かな手技、そして何より“道具”の力だった。 会場に展示された「壁紙道具7点セット」の前では、多くの参加者が足を止め、 カッターやローラー、ブラシなどの道具を、興味深そうに手に取っていた。 整然と並んだその姿は、DIY初心者にとっては頼もしい味方のようであり、 プロにとっては長年ともに歩んできた、馴染み深い相棒のようでもあった。 その光景を眺めながら私は、 こうした道具の普及が、これからの内装の現場に、またひとつ新しい変化をもたらすのだろう―― そんな予感を、静かに抱いていた。 |
| 小池氏は、「この7点セットがあれば、基本的には大丈夫です」と迷いなく断言し、 道具選びに不安を抱えていた参加者たちの表情を、ふっとやわらげた。 なかでも印象的だったのが、カッターに関するアドバイスだ。 「大きな段ボール用ではなく、小さくて薄い刃のものを使うと、仕上がりが格段にきれいになります」 そう語る声には、細部へのこだわりと実感が込められていた。 その言葉に、多くの参加者が深くうなずきながら耳を傾けていた。 ただの“道具”ではなく、それを選ぶ視点こそが、仕上がりを左右する―― そんな気づきが、静かに会場に広がっていくのが感じられた。 |
| 質疑応答の時間には、こんな質問が投げかけられた。 「糊付き壁紙と、通常の壁紙では、接着の強さに違いはありますか?」 これに対し、小池氏は迷いなく答えた。 「実は、糊付きのほうがむしろ均一に貼れて、DIYには向いているんです」 プロが使う壁紙は、施工前に機械で糊を塗布するのが一般的だが、 DIYではその工程がムラになりやすく、仕上がりに差が出てしまう。 その点、あらかじめ糊がついている壁紙なら、作業がスムーズで、失敗も少なくて済む。 小池氏のその一言に、参加者たちはほっとしたような表情を見せた。 肩の力が抜けたのか、会場の空気がふんわりとやわらいだ瞬間だった。 |
| さらに小池氏は、クッションフロア選びについても、こんなアドバイスを添えた。 「広い幅のものより、少し狭めのタイプを選んだほうが、初心者には扱いやすいですよ」 プロであれば、広幅の材料も難なく扱える。 けれど、慣れない手にはその大きさがかえって負担になり、思わぬ失敗につながることもある。 その微妙な“さじ加減”に寄り添った助言に、参加者たちは真剣な表情で耳を傾けていた。 |
| 司会としてこのやり取りのすべてを見届けながら、私は次第に確信するようになっていた。 内装の世界には、たしかに新しい時代が訪れつつある――と。 道具や知識が広く共有されることで、 誰もが住まいづくりに参加できる。そんな時代が、静かに、でも着実に近づいているのだ。 DIYが広がることで、プロの仕事が奪われるのではないか―― そんな不安の声もあるかもしれない。 けれど、実際にはその逆だと私は思っている。 自分の手で壁を貼り替え、空間を整える。 そんな経験を通して、暮らしへの愛着は深まり、 やがてプロに依頼する際の理解も、目線も、確実に変わっていく。 そうした往復が生まれ、信頼が育ち、 プロの領域は、もっと高度に、もっと創造的に磨かれていくはずだ。 この循環こそが、これからの内装業を豊かにしていく。 私は、そう信じてやまない。 |
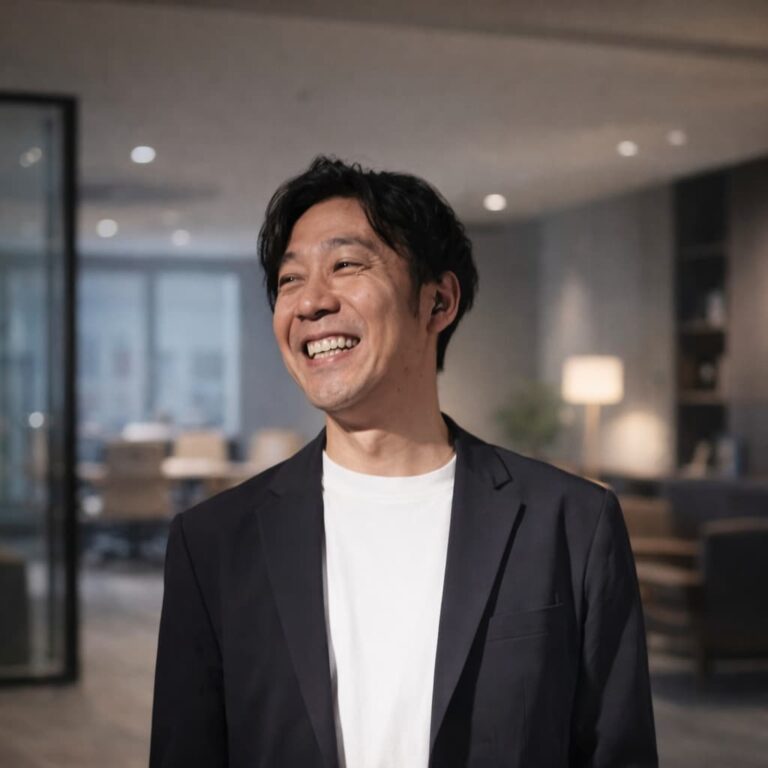
Point of View
小池氏が示してくださった道具選びの工夫や、糊付き壁紙の活用法には、初心者へのあたたかな配慮が感じられました。 細かな部分にまで宿るこだわりを惜しみなく伝え、参加者の不安をそっと安心へと変えてくださったことに、深く感謝しています。 その姿勢にはプロとしての矜持がにじみ、内装の未来を照らす静かな灯のように映りました。
編集後記
このセッションを振り返りながら、改めて感じたのは――
「住まいに自分の手を加える喜び」と、「プロに託す安心感」、そのどちらもが暮らしにとって欠かせないということ。
DIYの挑戦をあたたかく受けとめつつ、
細部に宿るこだわりや工夫を、惜しみなく語ってくださった登壇者の皆様。
その言葉のひとつひとつが、会場にいた誰かの背中をそっと押していたように思います。
あの時間に交わされた声が、それぞれの暮らしの中で、
少しずつ形になっていくことを願って――。

Author:山口剛
プロフィール
## 活動概要
山梨県出身。家業である壁紙卸売業を継承しながら、壁紙専門店「WALLPAPER STORE」のウェブ編集者として従事。幼少期より壁紙という素材に親しみ、成人後にその真の魅力を認識。「空間を一変させる壁紙の力」に感銘を受け、家業の発展とともにインテリア業界における新たな事業展開を開始した。
「WALLPAPER STORE」においては、壁紙の魅力をより広範囲の顧客層に訴求するため、ウェブサイトおよびSNSを通じた情報発信を担当。DIY愛好家のチームメンバー、ならびに施主の要望と生活様式に寄り添いながらインテリア空間を共創する「ウォールスタイリスト」と連携し、初心者にも取り組みやすいアイデアをブログおよび各種コンテンツを通じて提供している。
## 経歴
1983年、山梨県甲府市生まれ。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)卒業後、株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア株式会社)に新卒入社。事業企画部門において、中期経営計画の策定、予算管理、プロジェクトマネジメント等に従事。関連会社の統合、事業譲渡、合弁会社設立等、多岐にわたる企業戦略業務に携わり、豊富な実務経験を蓄積した。
## 個人について
家族との時間を大切にし、週末は息子のサッカー活動に積極的に参加している。また、浦和レッズの熱心なサポーターとして、週末のテレビ観戦を楽しみとしている。